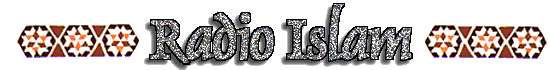ユダヤ民族3000年の悲劇の歴史を真に解決させるために
電網木村書店 Web無料公開 2000.6.2
第1部:解放50年式典が分裂した背景
第1章:身元不明で遺骨も灰も確認できない
「大量虐殺事件」9
「歴史上もっとも恥ずべき法の名による茶番狂言」という批判
ニュルンベルグ裁判の全体像についても、決定的な見なおしが必要であろう。
ナチス・ドイツの首脳部を裁いた主要法廷の国際軍事裁判について『東京裁判ハンドブック』では、東京裁判(正式には極東国際軍事裁判)と比較して、つぎのように評価している。
「判決が急がれたこともあり、膨大な証拠資料となった文書の山を前にして、ナチ体制の実態についての理解・認識が、裁判官側さらには検察官側でさえ必ずしも十分なものとはいえなかった」
『六〇〇万人は本当に死んだか』では、ニュルンベルグ裁判を「歴史上もっとも恥ずべき法の名による茶番狂言」と手きびしく断定している。これは決して、かたよった批判だとはきめつけがたい。
なぜならウィーバーの論文、「ニュルンベルグ裁判とホロコースト」によると、当時のアメリカの議会でも、という発言があった。「共和党の良心」として広くしられたタフト上院議員も、「勝者による復讐裁判」では正義の実現は不可能だと指摘していた。長年のソ連大使としても国際的に知られる外交官で歴史家のジョージ・F・ケナンも当時、ニュルンベルグ裁判の企画全体を、「ぞっとする」とか「あざけりの的」という表現をもちいて非難していた。
注目すべきことには、その当時、ユダヤ人のなかにもおなじ警告を発していた法律家がいた。ニューヨーク大学教授のミルトン・R・コンヴィッツは、ニュルンベルグ裁判が「もっとも原則的な法的手続きのおおくを無視している」として、つぎのように論じていた。
「われわれのナチスにたいする政策は、国際法とも、わが国の外交政策とも矛盾する。……ニュルンベルグ裁判は、人類が何千年もかかってきずきあげてきた正義についての基本的な概念にたいして、現実的な脅威をなしている」
すでに指摘したように日本のいわゆる平和主義者には一般的に、日本の戦争犯罪を裁いた東京裁判(極東軍事裁判)が不完全だったことの反省から、必要以上にニュルンベルグ裁判を美化してきた傾向がある。それは、ニュルンベルグ裁判がドイツの戦争責任を、日本のそれ以上にきびしく追及したという点だけに着目した評価だった。しかし、犯罪者にきびしいのはそれなりに結構だが、やってもいない犯罪を拷問で白状させたりするのは、一種の司法犯罪であり、法の権威をたかめるどころか、かえってあらたな無秩序の土台を提供することにつながりかねない。
ウィーバーは『ホロコースト/双方の言い分を聞こう』の中で、つぎの点を指摘している。
「ホロコースト物語がこれだけ長つづきした主要な理由の一つは、諸強国の政府が[イスラエルと]同様に、その物語の維持に利益を見いだしていたことにある。第二次世界大戦に勝利した諸強国――アメリカ、ソ連、イギリス――にとっては、かれらが撃ちやぶったヒトラーの政権をできるかぎり否定的にえがきだすほうが有利だった。ヒトラーの政権が、より凶悪で、より悪魔的に見えれば見えるほど、それに応じて連合国の主張が、より高貴な、より正当化されたものと見なされるのである」
ニュルンベルグ裁判の基本構造の土台には、やはり、「諸強国の政府」の「利益」があった。おおきくいえば戦後の全世界の勢力範囲あらそいという「利益」追求が先行した仕事だったからこそ、裁判のあり方にも欠陥が生じたのだ。
細部の問題点をあげれば本当にきりがない。『二〇世紀の大嘘』では、つぎのように要約している。
「おおくの事件では、“被告弁護人”がドイツ語を話せず法的資格のないアメリカ人だった。法廷には資格のある通訳が配置されていなかった。“検察当局”もまた法的資格をかいていたし、一〇人のアメリカ軍人で構成する“裁判官”も同様だった。一人だけ法的資格のある裁判官がいたが、その裁判官が証拠の認定にあたえる影響力は一番よわかった」
弁護団が記録を利用できず、被告に有利な証拠が突然「消滅」
被告側の弁護人は、しかも、裁判にはかかせない証拠の利用について、はなはだしく不利な立場におかれていた。
すでに紹介ずみの『ニュルンベルグ裁判』という本は、決して「ホロコースト」物語批判を目的として書かれたものではないが、そこにも事実の一端がしるされている。この本では、まず、連合軍が総力をあげてドイツの文書を押収し、「記録センター」に集中した状況をえがく。ところが法廷での実情は、つぎのように大変不公平なものであった。
「かくて検察側は、記録と記録保管所を自由に使えたわけであるが、これらについて弁護側のほうは、そんなものが存在することすら知りもしなかった。[中略]検察側はニュルンベルグでは(弁護団とは反対に)いつでも自分たちが必要と認めたものは、あらゆるところから手に入れることができたのである。ところが弁護団が見ることができるのは、無数の詳細なデータ、関連書類のうち[中略]、たいてい、有罪証拠物件だけで、多くはまったく知らないものばかりだった。これに反し、検察側はそれらを記録として証明できるのであった。被告側に有利な資料を探し出す可能性は、弁護団には皆無だった。
弁護団が、検察側の引用する記録を見せてほしいと要求しても、その記録が「消滅している」ことも、珍しくなかった。[中略]規約によれば、「重大な」箇所だけ翻訳すればよいことになっていて、(中略)テキストのひどい意味変更、歪曲、誤解が審理の際に生ずることも珍しくなかった。[中略]
連合国側に場合によっては不利となり、一方被告側の罪を軽減するのに適当と思える数千の記録は、突然姿を消してしまった。[中略]すでに一九四五年の時点で、記録が押収されたり、弁護団の手から取り上げられたり、あるいは盗まれたりしたという事実には、無数の証拠がある。[中略]
弁護団の証人や援助者は、ときどきころあいをみて、また執拗に脅迫を受けたりして、強引に出廷させてもらえなかったり、あるいは出廷させられることも珍しくなく、さらには自分たちの声明を検閲されたり、押収されたりしたうえで、検察側の証人にされたりした。一九五六年五月になってやっと刑務所入りをしたオズワルド・ポールは、アメリカおよびイギリス役人から尋問を受ける際、椅子に縛りつけられ、意識を失うほど殴りつけられ、足を踏まれ、ついにワルター・フンクの有罪を証明するものを文書で出すと約束するまで虐待された」
ドイツ人の法律家の場合には、そのうえに、ニュルンベルグ裁判が採用した英米式の訴訟手続きに不慣れだった。審理のすすめかたについて弁護団が抗議したときのジャクソン首席検事の「言い草」は、「数人の弁護人は元ナチスでありました」というものだった。結果として、そのさい、裁判長は弁護団の抗議を却下した。
『六〇〇万人は本当に死んだか』では、ニュルンベルグ裁判を「歴史上もっとも恥ずべき法の名による茶番狂言」と断定した理由をたくさんあげているが、そのなかでも、もっとも決定的とおもえるものは、つぎのような法廷の内部の構成員による告発であろう。
「ニュルンベルグ裁判の背景的事実を暴露したのは、その法廷の一つの首席裁判官だったアメリカ人の裁判官、ウェナストラム判事だった。かれは訴訟手続きの進行状況に愛想をつかして辞任し、アメリカに飛行機でもどったが、置き土産として、裁判にたいするかれの異議を逐一箇条書きでしるした声明を『シカゴ・トリビューン』紙上で発表した」
法廷構成の欠陥は早くも、当のニュールンベルグ裁判の進行中にも専門家から指摘され、メディア報道にもあらわれていたのだ。「正義は否定された」と主張するウェナストラム判事の「異議」は、いかにも判事らしい慎重な表現になっている。「箇条書き」の異議のなかから、もっとも核心的な法廷の構成の適格性にたいする疑問を要約すると、つぎのようである。
一、「国際検察局」のアメリカ人スタッフが「個人的な野心や復讐心のみによって動く」
一、「ニュルンベルグ裁判の法廷構成員の九〇%は、政治的または人種的な立場から、訴訟事件を利用しようする偏見にみちた人々だった」
一、「検察当局はあきらかに、どうすれば軍事法廷のすべての管理的地位を、帰化証明がきわめてあたらしい“アメリカ人”によって占めることができるかを心得ていた」し、それらの「“アメリカ人”」が「被告人たちにたいする敵意にみちた雰囲気をつくりだした」