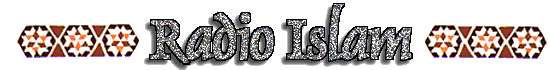ユダヤ民族3000年の悲劇の歴史を真に解決させるために
電網木村書店 Web無料公開 2000.6.2
第1部:解放50年式典が分裂した背景
第2章:「動機」「凶器」「現場」の説明は矛盾だらけ 5
【原著p126写真:10「ガス室」のブチぬかれた壁の跡。出入口に扉はない】
【原著p127写真:11「ガス室」天井の穴】
【原著p128写真:12 半地下風「ガス室」の入口と煙突】
【原著p129写真:13 裏へまわってみた煙突と「ガス室」の建物との位置関係】
「ロシア人が許可しない」という理由、いや、口実で実地検証なし
以上の「凶器」と「犯行現場」の問題にくわえて、さらに決定的なのは、現場での実地検証をまったくおこなわなかったという、おどろくべき手ぬき裁判の実態である。
第二次世界大戦終了後の一〇年間、ソ連は、アウシュヴィッツへの立ちいりを全面的に禁止していた。これだけ重大な、しかも、人類史はじまって以来ともいうべき一〇〇万人規模の大量殺人事件の告発だというのに、ニュルンベルグ裁判では、実地検証なしの判決をくだしていたのだ。証拠は「チクロンB」「自白」「陳述」だけである。
シュテーグリッヒ判事は、「西側同盟国がアウシュヴィッツ地域をまったく調査しなかった」理由について、「鉄のカーテン」を基本的な背景事情としてあげながらも、同時に、「部分的にはその理由で、部分的には別の理由で」という微妙な留保的表現をくわえている。「別の理由」をわたしなりにハッキリいえば、本式の調査をする気がなかったということにつきるのではなかろうか。たとえば『二〇世紀の大嘘』によると、当時のダッハウに一七カ月滞在したアメリカ戦争局の弁護士、ステファン・F・ピンターは、一九五九年になって、つぎのような弁解の文章を発表している。
「アウシュヴィッツにはガス室があるといわれたが、そこはロシア占領地域のなかだったし、ロシア人が許可しないという理由で、われわれは調査を禁じられていた」
シュテーグリッヒ判事も、このピンターの説明を『アウシュヴィッツ/判事の証拠調べ』で再引用し、この「ロシア人が許可しない」という状況説明に「かなりの不明確さがある」と指摘している。さらに別の箇所では、「カティンの森」で大量のポーランド将校の死体を発見した際のナチス・ドイツの態度を、ソ連の態度と対比し、その矛盾を鋭く指摘している。
「アウシュヴィッツについてのソ連の政策とは対照的に、ドイツ政府は、この犯罪の現場検証を世界中のジャーナリストや専門家がおこなえるようにし、写真撮影をゆるした。なぜソ連は、アウシュヴィッツの事件でおなじようにしなかったのか」
もう一方の西側諸国も決して真剣に、ロシア側に立ちいり調査の許可をもとめたわけではない。は、東西双方が必要とする陰微な共同作業だったからではなかろうか。また、国際軍事法廷という形式から考えれば、担当法廷の裁判長名で実地検証の命令がだされてしかるべきところだったが、その作業どころか議論の形跡もまったくない。
「原状保存」どころか部屋の壁はブチぬき、煙突は建てなおし
現在の日本の通常の刑事裁判に例をとれば、簡単な殺人事件でさえ被告の自白だけで判決をくだすわけにはいかない。「凶器」と「犯行現場」の自白があっても、その現場で「犯行の再現」をさせたりして、可能性を確認する。
アウシュヴィッツIには現在、「犯行現場」の「ガス室」だとして観光客が案内される半地下風の部屋がある。
シュテーグリッヒの著書『アウシュヴィッツ/判事の証拠調べ』によれば、最近の観光客が案内される「ガス室」が「つくり直されたものでしかないことを発見」したのは、フランスのフォーリソンである。隣室の焼却炉も、屋外の巨大な煙突も、戦後にポーランド政府が設置したものである。シュテーグリッヒはそれらを、「アウシュヴィッツ博物館の観光客には、もちろんのこと知らされてはいない重大な事実」と表現している。シュテーグリッヒの著書の末尾には、以上の設備の現状の写真が収録されている。
わたしの撮影技術でも写真(11:Web公開では省略)のような状況で、改造の跡はだれの目にもあきらかである。
「シャワールームの偽装」の痕跡もない。天井には空気ぬきのような穴(写真11:同前)があいているが、これはたしか、NHK3チャンネルの深夜劇場で放映した古いモノクロ映画で見た記憶がある。ドイツ兵がこれとおなじ形の穴から「チクロンB」のカンをほうりこむのだ。この穴もシュテーグリッヒによれば「あきらかに戦後につくられたもの」である。しかも、おどろいたことに、半分は「木製」である。これは致命的なことで、「チクロンB」の主成分の青酸ガスは、木材に浸透し、通過してしまうのである。
ところがもし、以上の疑問点のすべてを無視するとしても、被告が「チクロンB」をカンごとほうりこむという映画そのままの「犯行の再現」をおこなったとすれば、それだけで「疑わしきは無罪」とせざるをえないのである。なぜなら、「チクロンB」から青酸ガスを発生させるためには、カンから青酸ガスを吸着した木片などの「チップ」をだす必要がある。逆にいうと、「チップ」をカンのなかにもどしてフタをしてしまえば、青酸ガスの発生をとめることができる。「絶滅説」の「証言」によると、ユダヤ人たちは生命の危険を感じてドアに体当たりまでしたはずだから、必死で、なげこまれたカンからこぼれたはずの「チップ」をひろって元に戻したにちがいない。だから犯人は、「チップ」だけを「ガス室」の内部にいれなければならなかったのである。
以上のような「凶器」と「殺害現場」についての数々の疑問については、すでにカナダで係争中のツンデル裁判で、「ロイヒター報告」と題する「はじめての科学的、法医学的調査」の報告と鑑定証言がおこわれている。アウシュヴィッツの実地検証が、半世紀をへたいま実現しているのだが、その調査報告については、のちにまとめて紹介する。
ここでは、さらにもう一つ疑問を提出しておこう。
「ガス室」で殺したはずの大量の死体を、天を焦がすほどの煙を上げながら燃やしたはずの焼却炉のうえには、高い煙突が立っていたことになっている。たしかに現在もたかい煙突(写真12:同前)が立っている。しかし、シュテーグリッヒの指摘のとおりで、裏側にまわって見ると写真(12:同前)のように、なぜか煙突だけが地面から直接立っているのだ。下部は焼却炉につながっていない。
要するにすべて、観光名所用の模造品、または撮影用のオープンセットでしかないのだが、まったくのフィクションの小説を商品化した熱海の「お宮の松」とおなじ次元で論ずるわけにはいかない。こちらは歴史的「事実」の偽造であるし、あまりにも政治的性格のちがいがありすぎるのである。
しかも、現地では、現在も各所で改造工事がつづいていた。
うかつなことに帰国してから知人と話しているうちに思いだしたのだが、「ドイツが新たに4億円拠出発表/アウシュヴィッツ強制収容所修復」(毎日94・11・9夕)というみじかい記事が、わたしの「ホロコースト」ファイルのなかにもあった。
記事中にはより正確に「新たに六百八十万マルク(約四億四千万円)を拠出」とある。しかも、「過去の分と合わせ、ドイツ政府の拠出額は一千万マルク(約六億四千万円」であり、「民放の呼び掛けに応じ、民間からの寄付金がこれまでに約二千万マルク(約十二億八千万円)に上っている」というのだから、さしひき、過去には合計約二億円だった拠出額が、民間の寄付もあわせて今回一挙に約一七億二〇〇〇万円以上になる計算だ。これはまた、かつてない大工事の資金である。さらにこれは、「(一九九五年)一月の五十周年」を意識しての修復資金拠出なのである。
もしかすると「復元」と称して、これまでよりもはるかに精巧な歴史偽造が進行する可能性がある。それがふたたび、「アウシュヴィッツ博物館の観光客には、もちろんのこと知らされてはいない重大な事実」にならないように、おおいに危惧して見まもるべきであろう。
煙突については『シンドラーのリスト』で、モノクロ画面の中で強調したい部分に色をつけるという特殊効果がつかわれていた。映画のアウシュヴィッツの茶色のたかい煙突からは、ゆらめく黄色と赤の炎をまきこんで、真っ黒の煙がゴウゴウと不吉な音を立てて舞いあがっていた。あの煙突はハリウッドのオープンセットであろう。たかい煙突からモクモクと煙が天にあがる場面は、いわばこの種の映画の「決まりシーン」である。「煙突の煙」も水戸黄門の「葵のご紋」である。
ところが『アウシュヴィッツ・神話と事実』によれば、一九七二年にアメリカの中央情報局(CIA)が情報公開した資料の中に、米軍の飛行機がアウシュヴィッツの上空で撮影した航空写真が何枚もあった。戦争末期の一九四四年、まさに「大量虐殺」と「死体焼却」の真っ最中だったはずの頃の「ことなる時期」に、何度も上空を飛んで撮影したものだ。だがそのどれにも、「まったく煙が写っていない」のである。
おなじく一九四四年の一月から一二月までアウシュヴィッツで勤務した体験にもとづいて『アウシュヴィッツの嘘』を執筆した元ドイツ軍中尉、ティエス・クリストファーセンは、当時もつたわっていた「虐殺」と「焼却」の噂を母親から聞いた。そこで、真相を確かめるために「収容所全体を歩きまわって、すべてのかまどや煙突を調べたが、なにも発見できなかった」と回想している。